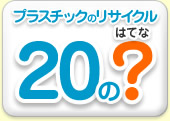廃プラスチックの処理は、これからどうなっていきますか?
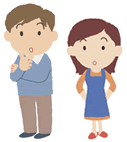
廃プラをめぐる課題の整理
将来を予測する前に、まず現状の課題を整理しておきましょう。
容リ法の枠組みにおける廃プラスチック(一般廃棄物)の処理をめぐる課題とは、「その他プラ」をどうするか、ほとんどこの1点に尽きると言ってもよいのではないでしょうか。
現状では、いろいろなものが一緒になっている「その他プラ」を強引にマテリアルリサイクルしてしまっていますが、これまで見てきたように、無理なリサイクルはLCA的にみてエネルギー資源や環境負荷の低減にならないうえ、社会的コストの増大にもつながります。
なぜそんなことになってしまうのかを整理すると、大きく2つの背景が考えられます。
(1)廃プラスチックのリサイクルを「その他プラ」で一括りに考えている
家庭から出る「その他プラ」は食品残渣による汚れが付いていたり、多種類のプラスチックが混合していたり、包装材自体が多層構造の複合材であることが多いため、マテリアルリサイクルには向かないものです。このようなプラスチックを一括で集めてリサイクルすること自体に無理があるのです。
(2)リサイクル業者を決める入札制度でマテリアルリサイクルが優先されている※1
前項で示した(社)プラスチック処理促進協会の結果だけでなく、(財)日本容器包装リサイクル協会が行ったLCA評価※2からも、材料リサイクルが優先される根拠はありません。しかし、今は「とにかく材料リサイクル」になってしまっています。
※1:平成11年3月、産業構造審議会で示された「再商品化手法の考え方」による。
※2:「プラスチック製容器包装再商品化手法に関する環境負荷等の検討」(平成19年6月)
「分別(ふんべつ)」ある分別と適正処理※3
では、どうすればよいのでしょうか。
「集めたものをどうリサイクルするか」から、「どのようなものを何にリサイクルするために集めるか」へ、発想の転換が必要です。マテリアルリサイクルをするのであれば、PETボトルや白色トレイのように、わかりやすく分別しやすい単一素材でできているものを集め、その他大勢のプラはケミカルリサイクルや熱回収を行うというように、廃プラ処理の手法をLCAの視点で見直すことが必要です。そのうえで、リサイクルは排出状態や素材構成をもとに行うべきなのです。
※3:全国都市清掃会議 特別講演(2006年)で、田中勝教授(当時:岡山大学大学院)が提言。
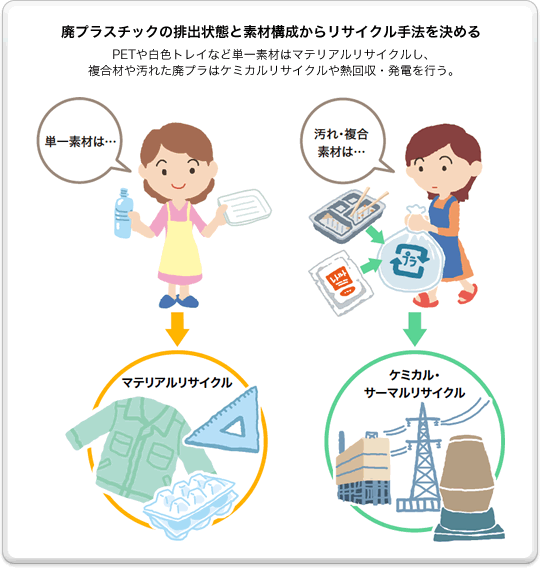
複合材は、今の技術で簡単に剥がせないのかなあ?
あるいは、リサイクルしにくいからなるべく使わないとか。

プラスチック製容器包装の素材は、安全・安心の観点から必要に応じて使い分けるため、いろいろな種類があります。そして複合材は、中身の品質や安全性を守るため、簡単に剥がれるような構造にはなっていません。
そもそも複合材は軽く、かさが低いことでリデュースに貢献しています。同じ機能を単一素材で持たせようとすれば厚くするしかなく、重さも体積も増えてしまいます。リサイクルありきで物事を見てしまうと、手段が目的になってしまうような本末転倒が起こります。
今、求められているのは、プラスチックそれぞれの役割・機能を評価したうえで、資源エネルギーや環境に対してできるかぎり配慮をし、合理的な処理をしていくことではないでしょうか。
そのためにもLCAは有効な指標になります。
容器包装だけじゃなく、
プラスチック製品もリサイクルされるようになるの?
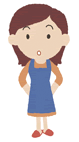
「製品プラ」の現状
容器包装プラスチック以外にプラスチックを使用した製品がたくさんあります。「製品プラ」と呼ばれる、これらプラスチック製品のリサイクルがあまり進んでいません。「同じプラスチックなのに、なぜ?」と思う方もいるでしょう。
製品プラもリサイクルできなくはないのです。単一素材で、ある程度まとまった量が排出されるのであれば、マテリアルリサイクルも可能です。しかし、ほとんどの自治体で、容器包装以外の製品プラが集まる量は非常に少ないのではないでしょうか。
もともと製品プラは廃棄されることを前提として作られていません。バケツや弁当箱をしょっちゅう買い換える人はいないでしょうし、プラスチック製品は破損や変形がなければ10年でも使えます。いつ廃棄されるかわからないものに対してメーカーにリサイクル費用を負担させるのは現実的ではないでしょう。もしリサイクルをするとしたら、熱回収や発電など、ある程度経済の効率性もあって環境負荷の少ないやり方を選択するのがベターです。
多くの自治体で、製品プラは「燃やすごみ」にしています。製品プラを焼却して量を減らすこと、これは埋立処分場の延命に大きく貢献します。また、廃プラを燃焼させることで焼却炉の助燃材が節約できるというメリットもあります。カロリーの安定しているRPF化も有効な利用法です。
一方で近年、海洋プラスチックごみ、気候変動、資源の枯渇といった問題がクローズアップされています。これら問題の解決のためにプラスチックの3R(リデュース、リユース、リサイクル)を進め、再生可能資源を使っていくことを目指し2022年4月から「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラ新法)」が施行されました。
えらんで、減らして、リサイクル「プラ新法」スタート

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラ新法)」は、プラスチックのライフサイクル(設計、製造、販売・提供、排出・分別、回収、リサイクル)全体に、事業者、消費者、国、地方公共団体等のすべての関係主体が参画し、相互に連携しながら環境整備を進めることと、相乗効果を高めていくことが重要なので、それぞれの立場での役割を明確にすることを規定しています。
私たち消費者の役割は
①プラスチック使用製品の使用の合理化によりプラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制すること
②事業者及び市町村双方の回収ルートに適した分別排出をすること
③認定プラスチック使用製品を使用すること
以上に努めなければなりません。
その他の関係主体の役割ほか、詳しいことは「環境省 ウェブサイト」
製品プラは、リサイクルのしやすさ、つまり単一素材である程度まとまって集めるということに難しさがありますが、今後みんなの力を合わせて取り組みを広げてゆくことがとても重要です。
プラスチックと
どう付き合っていくか、
使い終わったプラスチックを
いかに有効利用するか。

暮らしになくては
ならないものだから、
これからも注目していこうと
思います。